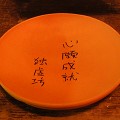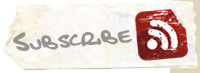平野神社の桜花祭へ行ってきました。もちろん、ひとりで。
平野神社の周囲はかつて、辺り一面が長閑な農地だったそうです。
住宅地&西大路通&そこを通る立命の●●学生に囲まれる現在からは想像が困難ですが、
佐野藤右衛門の分厚い桜本によると、実に昭和初期に至るまで農村の雰囲気は残ってたとか。
へ~、という話ではあります。ただ 「元農村」 が全く想像つかないかといえば、そうでもありません。
すぐ隣の北野天満宮には、道真以前から五穀豊穣を祈願する雷神信仰が存在したというし、
秋のずいき祭に登場するずいき神輿などは、正しくこの地の旧来の風土性を現在へ伝えるものです。
で、そんな 「農」 or 「土」 なこの地の歴史と性質を感じさせてくれるもう一つのエレメントこそ、
当の平野神社の名物 or アイデンティティ or レゾンデートルとして有名な、桜ではないでしょうか。
「平凡苗字神社」 と、当サイトで阿呆なタグをつけてるほど平凡な苗字の如きその名に反し、
桓武天皇によって平安遷都と同時に奈良から勧請された、極めてロイヤルな由緒を誇る、平野神社。
名物の桜もまた、花山天皇による手植えに始まるという、ロイヤルな由緒を誇るものであります。
応仁の乱の際には、西軍の拠点に近いため一度は社殿や領地ごとズタボロと化しましたが、
江戸期に至ると、宮司として社の再興を果たした西洞院時慶が、現在のベースとなる桜苑を整備。
さらに近くの西陣が織物で隆盛を誇り始めると、西陣に密着した桜の名所として、発展を果たしました。
故にというか何というか、私にはいかにも京都的な 「街中の桜」 に見える平野の桜ですが、
戦後すぐの頃は桜樹を取っ払って芋が植えられたというくらい、元来この土地は肥沃なのであり、
桜も芋も育んだその肥沃さは、農地に囲まれてたかつての時代に醸成されたものかも知れません。
そんな平野神社、桜シーズンの真っ只中に、祭を開催してます。その名もずばり、桜花祭。
花山天皇の時代に始まったとも言われてる祭礼を、大正期に復活させる形で開始されたこの祭は、
恐らく明治の上知以前の神領地だったエリアを、古式に則った祭礼列が回るというもの。
都市化された元の農地を、まるで桜を育んでくれた礼をするように、神が巡幸するわけです。
そんな桜花祭、ユルく追尾すると共に、桜苑もユルく鑑賞してきました。