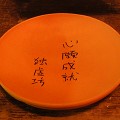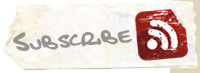隨心院のはねず踊りへ行ってきました。もちろん、ひとりで。

隨心院のはねず踊りへ行ってきました。もちろん、ひとりで。
隨心院。
山科区小野にある、真言宗善通寺派大本山の寺院です。
「小野」という地名がまんまで示しているように、かの絶世の美女・小野小町ゆかりの寺であります。
もらいまくった恋文を下張りにした文張地蔵尊像や、もらいまくった恋文を埋めてできた文塚など、
絶世の美女ならではの豪気なアイテムは、この寺にもいろいろ存在。
男から見ると不条理極まるエピソードである「深草の少将百夜通い」の舞台も、ここです。
「私が欲しければ、私の家まで100回来い」と。で、少将は毎夜通ったと。でも、99回目に凍死したと。
99回目の夜に雪が降ったことが不条理なのか、100回も来いというのがそもそも不条理なのか。
「無論、後者だ。30回くらいにまけてやれ」と説教したくなるあなたは多分、私の同志でしょうが、
でも同時に多分、もてないんでしょうね。
とにかくそんな「百夜通い」のエピソードをを主題にしたのが、この日に行われた、はねず踊り。
悲しい物語を、地元の少女たちが深草少将と小野小町に扮して、踊ってくれます。
「跳ねない踊り」のことかと思ってたら、かつては随心院の梅を「はねず」と呼んでいたとか。
で、その「はねず」が咲く頃に踊るから、はねず踊り、と。
一時衰退しましたが、昭和48年に地元の努力で復活したそうです。

随心院総門。
地下鉄東西線小野駅を出て、実に醍醐感溢れる殺伐とした街並を5分ほど歩くと、着きます。
深草からここまで通って死んだのなら、毎晩稲荷山でも越えてたのかと思ってしまいますが、
深草少将は昔の大岩街道、のちに東海道本線旧線、現在は名神高速のルートを歩いてたそうです。
死ぬか?それで。

参道のタダ見ゾーンの梅。
奥の方にちらっと見える白いテントのとこで、拝観・梅園入園料込の1000円を支払います。
一休寺の一休善哉並の強気な値段設定ですが、中心部から離れた寺はいろいろ大変なんでしょう。

入ってすぐの境内では、主催者であるはねず踊り保存会が、はねずういろうなるものを販売。
ミス小町なる着物姿の女性が前面に立ち、客寄せと呼び込みを頑張ってます。
ミス小町、はねず踊りの司会進行も担当。
さらには、イベント終了間際「はねずういろう完売間近です」と何度も絶叫したりと、大活躍でした。

はねずういろう、もちろん買います、もちろん食います。
もっとキレイに食え&キレイに撮れという話ですが。
「その場で食う」と言うと、売り手のおばちゃんが竹筒の底に空気穴を開けてくれました。
空気穴に空気入れて押し出して食うのもよし、バキューム吸引して食うのもよし。私は、吸引派です。
見た目の通り、ういろうというより黒砂糖が入った寒天の味。

はねずういろうの外にも、餅やぜんざいの販売もありました。
餅1パック500円、ぜんざい200円でしたでしょうか。
こちらはういろう以上に人気で、昼の1時半頃には両方とも売り切れ。

薬医門前に設置された、はねず踊り会場。
立ってる人が全員座ったら、丁度椅子が埋まるという感じの人出です。
マスコミっぽいのも含めて、カメラマンがウジャウジャいることは言うまでもありません。

東日本大震災の被災者へ黙祷してから始まったはねず踊り。
踊るのは、地元の小学生4~6年の女の子たちです。
不条理かつ残酷な内容を、わらべうたに乗せ、可愛らしく踊ってくれます。

童謡の多くが残酷なテーマを内包してるのは周知のことですが、
男にとっては残酷だけど女にとってはそうでもない内容を小さい女の子に踊られると、
男にとってはより残酷で女にとってはよりそうでもないという感慨が湧いて来るような、来ないような。
あ、例によってまともな写真や紹介が欲しければ、まともなサイトをお当たり下さい。
最前線で重そうなカメラで撮ってるうちの誰かが、アップしてるはずです。

はねず踊りに続いては、今様。一転して、大人の舞を見せてくれます。
ここまでが、基本の演目。当日は、何とこれの4回まわし。大変です。

4回あるうち、11時の回と13時半の回には雅楽と舞踊が追加されてました。
雅楽は、市比賣神社のいちひめ雅楽会が上演。
極めて中華 or 大陸的に見える衣装とアクションが、背景の赤黒縞と妙なマッチングを見せてます。


雅楽の演目は、蘭陵王と納曽利。といっても、どっちも何がなんだか私は知りませんが。
もはやロックンロールな域に入った荒々しいポージングが、映えます。

雅楽の次は舞踏なんですが、こちらは地元の婦人会らしき方々が出演。
バズーカみたいなレンズを露骨に仕舞いはじめるおっさん多出なのが、笑えました。

梅園。実に見頃です。
撮ってないですが、奥に有料の茶屋があります。確か料金、500円。

人がいなさそうに見えますが、実際には物凄い込み方です。時に、レミング状態。
そもそも狭い上に、演目の合間に人が集中するためでしょう。
15時の回で子供が踊ってる間に行くと、結構空いてました。

1000円払ったんだから、あんまり興味ないですが書院や本堂も拝みます。
小野小町グッズ売店や小野小町化粧品ポスターや小野小町屏風などが並ぶ庫裡を通り抜け、
歩くたびにキシキシと音を立てる堂内を歩きます。

表書院から、本堂と庭を望む。

池。そして、池を見る人。
客層は、中高年多し。
内訳は、烏合。地元臭は濃いですが、和装の観光客や団体客なんかもいます。
観光団体は、わかりやすい老人団体。
若いカップルや夫婦は、地元テイストが濃厚ななごみな雰囲気。
カップル率は、そこそこ。高くもなく低くもなく。
数的にも雰囲気的にもプレッシャーを感じるようなレベルではありません。
単独、カメラマンの男ばっかり。ただしカメラマンじゃないのも少しいました。
そんな随心院のはねず踊り。
好きな人と観たら、より小野小町なんでしょう。
でも、ひとりで観ても、小野小町です。

|
|
|
【客層】 (客層表記について) カップル:1 女性グループ:若干 男性グループ:若干(限りなく皆無) 混成グループ:0 修学旅行生:若干(地元の小学生) 中高年夫婦:2 中高年女性グループ:2 中高年団体 or グループ:2(烏合) 単身女性:若干 単身男性:1 |
【ひとりに向いてる度】 ★★★ 色気的にはなし。 ただし、あんまり小さい娘を熟視して、 あらぬ疑いをかけられても、知らない。 【条件】 |

随心院
京都府京都市山科区小野御霊町35
9:00~16:30
京都市営地下鉄小野駅 徒歩5分
公式サイト 小野小町ゆかりの門跡寺院 隨心院
Wikipedia 随心院