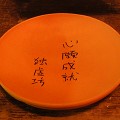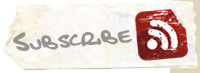葵祭・路頭の儀を追尾してみました。もちろん、ひとりで。 (2)

葵祭・路頭の儀のフル追尾、続きです。
京都の人にとって、葵祭は「それほどでもない」んだそうです。
『京都大不満』 という本に、そう書いてありました。曰く、三大祭の中では「それほどでもない」。
祇園祭は愛着度が高い、と。誰が見てもわかります。で、時代祭は全然だ、と。これもわかります。
が、葵祭の「それほどでもない」という感じは、ちょっと微妙なニュアンスの世界かも知れません。
しかし、私にはわかる気がします。一応、勅祭が行われる八幡の民としては、わかる気がします。
勅祭って基本、じっと見るしかしょうがないんですよね。
ほとんど無形無実とはいえ皇族が関わる祭ですから、平民はおいそれと参加できないわけです。
その割には学生バイトが動員されまくってるし、ボランティアの方も多く関わってるんでしょうが、
自分達で作る自分達の自主的な祭というのとは、何かが決定的に違う。
今でも「お上の祭」なわけです。当の「お上」が御所にいなくなっても、「お上の祭」なわけです。
神が街を巡幸することはなく、あるのはコスプレ行列のみ。それらをただ、見る。じっと、見る。
牛車を、風流傘を、知らん間に知らん所で決定される斎王代などを、つくづくと見る。
「見る」側の優位性がとかく強調され、無能ゆえの万能感を膨張しやすい現代において、
葵祭は、見ることしか出来ない平民の無力さを改めて教える儀礼なのかもしれません(大層な)。
5月のよく晴れた都大路を、コスプレ追いかけて走りまわる、そのみっともなさ。
もちろん現代の我々は、そのみっともなさをマゾヒスティックに享受する自由も持ってるわけですが。
社頭の儀を終えた下鴨神社からゴールの上賀茂神社までのパレード後半戦、
同志のあなたもマゾヒスティックに、無能に、追走してみますか。

行列が下鴨神社へ入り、社頭の儀を執り行い始めて、約2時間。
下鴨本通では見物客が路上にゴザ敷いたりして、今か今かとパレードの再開を待ち受けてます。
ここでも中国人グループをよく見かけました。あと、実に観光客な方々も。
ピザトーストで一応燃料補給しましたが、いきなり気合で負けそうです・・・。

14時ごろ、行列が現われました。後半戦、開始です。
ここからしばらくは平安でも雅でもない、普通に都市的な景観の下鴨本通を北上します。
手前の馬は、京都府警の平安騎馬隊。現世における馬路、いやマジの行列護衛です。

路上のど真ん中で謎の存在感を放つ、山城使の傘。
北上すると、地元の人の見物が目立つようになります。「来てはるで」と、家から出てくるみたいな。
必死で走り回る観光客の方も全然減りませんけどね。

狭い裏道から見ると、すごく大きく見える牛車。こちらは御所車。
霊元天皇より下賜されたもので、勅使が乗用した超クラシックカーであります。
下鴨本通は風情がないですが、一筋ずらして細い道の奥からチラ見で見る行列は、すごく味。

「バス乗った方が早いやろか・・・」と思ってるはずはない、駒女。
バスの中から観たらさぞ面白い光景に思えますが、実際にこんな状況に出くわすと
「もういい加減にしてくれよ、公共交通くらい普通に動かせろよ」とか思ってるんですよね。

「自転車乗った方が早いやろか・・・」と思ってるはずはない、陪従。
下鴨本通を北上した行列は、北大路との交差点で左折、そのまま賀茂川まで西進します。
北大路は、さらに地元テイストが強い感じでしょうか。行列の人と沿道の人が話してたり。

で、賀茂川を渡る北大路橋は、大混雑。皆さん、斎王代が来るのを待ってます。
背後には、平安時代のままの景観の賀茂川堤、そこで斎王代を撮ろうとする人民で、いっぱい。
橋、見物客は歩道しか歩けません。渡りきるのに根性、いります。

で、賀茂川堤へ突入した斎王列。ご覧の通りの有様です。後から見ると、ちょっと怖い。
自分ではなく、見てる本人の頭の中にしかないものを見てる視線が、刺さる。それも、大量に。
考えただけで、恐ろしい。私が行列のバイトやったら、夜とかうなされそうです。
もっとも当人達は衣装の重さと長距離歩行の疲労で、細かいことなどわからんかも知れませんが。

新緑に映える女人列。斎王代を囲む形で47人の女人が平安丸出しで付き従います。
トップ&前の画像だと無茶苦茶混んで見える賀茂川堤ですが、実際はそうでもありません。
むしろ、狭い割には空いてます。特に川側はスイスイ移動が可能です。
ただ行列の進むスピードは、結構速め。立ち止まって撮ってると、すぐ先へ行ってしまいます。

恐れ多きことにすぐそばで見た、第56代斎王代。ご苦労様でございます。
斎王とは、平安時代に皇室から賀茂神社へ巫女として奉仕した、未婚の内親王。
平安末期以降は現代まで延々と途絶、しかし1953年、客寄せ観光対策として復活しました。
本物の内親王は来てくれないから、代理。だから、斎王代。
良家の子女のみが、担当します。「なりたい」とか言っても、誰でもなれるものではありません。
「チャンスは平等に」とか言っても、駄目です。「あきらめない」とか言っても、駄目です。
それでもどうしてもなりたいという方は、いっそ来世へワープした方が早道かも知れません。

賀茂川堤を斜めに北上した行列は、御園橋を渡って、いよいよゴールの上賀茂神社へ向かいます。
遠くに橋を渡ってる牛車が見えるでしょうか。人も少なく、実にのどかな風景です。

橋と見物客以外は平安時代そのままかも知れない、山、馬、駒女。
あ、そういえば葵祭の予算は総額2900万円と一社提供でも何とかなりそうなお値段ですが、
だからといって親の会社に丸買いさせても多分、斎王代にはなれません (しつこい)。
何故かは知りませんが、でも何となくそう思えるようになれば、あなたも立派な京都人(嘘)。

さらに人が少なくなった上賀茂神社で行列の到着を見届け・・・と思ったら、実際はこんな感じ。
そんなに狭いところでもないですが、えらい混雑。みんな、走馬目当てでしょうか。

16時、行列が上賀茂神社に到着。お疲れ様ですが、足だけで追いかけた私も疲れました。
ここから先は下鴨と同じく、社頭の儀。勅使の祝詞奏上や御幣物奉納などの、真の雅タイムです。
もちろん、タダ見は困難。ですが、馬の走りを奉納する走馬神事は結構、見えるんですよ。

全然見えない境内の中で全然わからない神事が行われてる間、ボケ~っと走馬を待ちます。
千円の走馬用の有料席は人が少ないなあとか、結構ベタな祭りの屋台も並んでるなあとか、
定住系の白人がやたら多いなあ+八幡は白人以外の外人がやたら多いんだけどなあとか、
色々思いながら突っ立つこと1時間。鳥居の前に、花傘とコスプレ護衛がいるの、見えるでしょうか。

やっとこさ始まった、走馬の儀。競馬神事の埒ではなく、表参道を使って行われます。
一の鳥居から二の鳥居までが、直線コース。ここは有料席でないとほぼ見えません。
二の鳥居で60℃ほど曲がり社務所前へ抜けるあたりが、いわば無料ゾーン。
カーブがあるため、大抵の馬は無料ゾーンをゆっくり走ります。全然迫力ありません。
ただし、カーブを曲がりきれない馬がいて、鳥居付近に突っ込む様を見れたりするのは、味。
走馬が終われば祭は終了。バスはどうせ混むので、離れたところまでしばらく歩きました。
大宮通を歩いてると今宮祭の神輿に出会いましたが、追いかける体力はもうありませんでした。
と、行列をコンプする形で追っかけてみましたが、当然ながら、しんどいですよ。
自転車使えば楽な気もしますが、人ごみへ特攻する時が面倒だし、停めるのはもっと面倒です。
ひとりであっても、御所か糺の森で行列のディティールを丁寧に眺めるのが、やはり正道でしょう。
客層は、何かもう、よくわかりません。場所によって違うし、そもそも人多過ぎるし。
カップル、少なめ。いや結構いますが、それ以外の人間も無茶苦茶に多いため、目立ちません。
他の属性もほぼ同様。もう本当に、人のことなんかどうでもよくなります。
単独男性のメインは、おっさんカメラマン。あとは何か、気違いの男。
単独女性は、たぶん普通の娘。というか、本当に埋没してて印象がありません。
お勧めの場所は、御所か賀茂川堤でしょうか。とにかく広くて逃げ場がある所が、いいですよ。
丸太町通・河原町通・下鴨本通など、混雑が凄くて逃げ道の少ない大通りは、
よっぽど凡庸な都市景観をバックに行列を楽しみたい変態さんでもない限り、おすすめしません。
そんな葵祭、路頭の儀。
好きな人と見たら、より勅祭なんでしょう。
でも、ひとりで見ても、勅祭です。

|
|
| 【客層】 (客層表記について) カップル:1 女性グループ:1 男性グループ:若干 混成グループ:若干 修学旅行生:0 (子供は子連れとして中高年Grに含) 中高年夫婦:2 中高年女性グループ:1 中高年団体 or グループ:4 単身女性:若干 単身男性:1 |
【ひとりに向いてる度】 ★★★ 人圧が凄まじい。 色気のプレッシャーは、ほぼ気にならない。 というか、細かいことがもう気にならない。 しばらく平日開催となる来年以降はどうなるか知らないが、 基本、ただただ体力勝負。 【条件】 |

下鴨神社
京都市左京区下鴨泉川町
京阪電車&叡山電鉄 出町柳駅下車 徒歩12分
京都市バス 下鴨神社前 下車5分
下鴨神社 公式 世界遺産 下鴨神社
Wikipedia 賀茂御祖神社
上賀茂神社
北区上賀茂本山339
市バス・京都バス 上賀茂神社前 下車すぐ
上賀茂神社 公式
上賀茂神社(賀茂別雷神社)公式Webサイト
Wikipedia 賀茂別雷神社