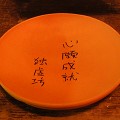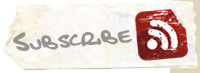清水寺での盂蘭盆会・六斎念仏奉納へ行ってきました。もちろん、ひとりで。

清水寺での盂蘭盆会・六斉念仏奉納へ行ってきました。もちろん、ひとりで。
盂蘭盆会。平仮名だと、うらぼんえ。いわゆる、お盆のことであります。
なのにトップ画像は、イカついお面の方が刀を構えてて、物騒この上ないのは、何故。
それにそもそも、清水寺って念仏の寺だったっけ。
そう思っていただけると嬉しいんですが、これはいわゆる京都の六斎念仏であります。
元来は殺生禁断や謹慎を定めた「六斎日」に、念仏を修するところから始まった、六斎念仏。
それが時代を経て踊り念仏へ変容し、さらに「見せる」ことを意識し始めて、芸能化。
京都は最先端の芸能が集結する場でしたから、一旦芸能化するとその流れは止まらず、
長唄・地唄・歌舞伎などを貪欲に吸収、あげくセリフ付きの狂言まで取り入れてしまったという、
特殊過ぎる発展をした民俗芸能というか、信仰行事というか、まあそんなんであります。
現在も市内のあちこちに保存会があり、お盆を中心に奉納演舞を行なってますが、
「清水の舞台」を文字通りの桧舞台とした、こちらの清水寺盂蘭盆会奉納も、そのひとつ。
この舞台での奉納は、かつて六斎の最高の栄誉だったそうで、それを平成十年に復活。
中堂寺六斎会が、牛若丸と弁慶の対決を描いた『橋弁慶』を上演することでも知られます。
そう、トップ画像のイカついマスクマンは、弁慶なのです。

えとですね、清水寺ってね、山の上にあるんですよ。知ってましたか。
くそ暑い中を山登りするとね、体力が失われるわけですよ。なので、まずは腹ごしらえです。
中華そばで有名な『味の小松』で、冷麺。900円ぐらいでしたでしょうか。
外の二年坂は賑やかですが、店の中はひっそりしてます。

冷麺パワーで、何とか上りきった清水坂&仁王門前。
夏の閑散期を何とかしようと仕組まれた「京の七夕」の短冊が、あちこちで揺れてます。
仕掛けのかいあってか、とんでもない暑さにもかかわらず、清水坂を上る者、多数。

300円払って入った、清水の舞台上。まるで市民プールのような芋洗い状態です。
左側で舞台に座り込んでるのは、もちろん六斎の登場を待つ人たちであります。

15時ジャスト、まずは本堂の中で上鳥羽の橋上鉦講中の奉納が始まります。
上鳥羽の橋上鉦講中は、「念仏へ帰れ」派というか、とにかく念仏主体の念仏六斎です。
六斎念仏の、念仏六斎。大して芸能全開なのは、芸能六斎。

シンプルな読経と太鼓で、じっくりと念仏を唱えていきます。
本堂の中では、東日本大震災の慰霊が行なわれてました。

15時半あたりからは、舞台を「舞台」へ移して、中堂寺六斎念仏の奉納が始まります。
こちらは、バリバリの芸能六斎。人数も一気に増えて、老若男女数十名が、舞台に集結。
頭目らしきおっちゃんが大太鼓を「ドーン」と一発決めるだけで、場はもうカーニバル状態へ。
『発願』 『六段』 『すがらき』 『石橋』 と、演目は進みます。

そして出ました、『橋弁慶』。子役の牛若丸と、怖過ぎる面の弁慶の、死闘であります。
中堂寺六斎は戦前の一時期、すぐ近所の壬生寺・壬生狂言を60年ものあいだ継承してたそうで、
その時の遺産として、壬生狂言から抜粋したかたちで無言劇が演じられます。

時々床で足を滑らせ、見る者を冷や冷やさせながらも、牛若丸は大熱演。
弁慶の迫力は、言うまでもなし。ちなみにこの面、壬生寺からの寄贈。さすがにイカツさが、違います。
二人の対決は五条大橋が有名ですが、この清水の舞台でも一戦交えたという説もあるんだとか。

『橋弁慶』に続いては、長唄の同名曲を太鼓曲化した『越後獅子』、そして『越後さらし』。
『越後さらし』は、新規に創作された、小学生たちによる二枚のさらしを交互に振る演舞。
写真だと新体操のリボンみたいに見えますが、実際はもうちょっと迫力あります。

そして、これぞ六斎の基本にして最高の醍醐味、『四つ太鼓』。
太鼓を片手だけで叩く一本ぶち、両手を使う二本ぶち、二人同時に打つ相打ち、
太鼓を六つに増やしての六つ太鼓、そして高度なぶち捌きが冴えるデレデレ太鼓へ。
幼児のおどけた演舞から、少女達の熱演、そして青年のハードな叩きっぷりまで、
とにかく、太鼓、太鼓、太鼓であります。

続いては、『祇園囃子』。月鉾と函谷鉾の曲を、抜粋して六斎風にアレンジしたんだとか。
、何故か重鎮クラスの二人が、太鼓バトルにも見える緊迫感溢れるプレイを展開します。

『祇園囃子』では、中盤に何と、棒振りも登場します。
祇園祭の棒振りといえば綾傘鉾ですが、あそこの棒振りは中堂寺の近所の壬生六斎が担当。
何か関係あるんでしょうか。こちらの棒振りも、厄除け祈願でブンブン棒を振り回していました。

大人の凄技が連発されたあとは、子供がコミカルに活躍する 『猿廻し』。
中央の大太鼓を囲む形で、猿廻しが踊るような微笑ませ言い演舞を見せてくれます。

で、いよいよクライマックス、『獅子と土蜘蛛』の始まりです。
二人羽織の獅子さんたち、ご入場。客を威嚇したり、逆立ちしたりと、多彩なアクションを見せます。
六斎ごとに善玉だったり悪玉だったりする獅子ですが、こちらは善玉。

清水の舞台上で見事に決められた、六段の碁盤乗り。
もう、見てるほうも、怖い。離れて見ると、舞台が微妙に傾いてるのがわかるから、余計に怖い。
ちなみに六段の碁盤乗りは、約20年ぶりの快挙だとか。

碁盤乗りを決めて休憩する獅子を、土蜘蛛が攻撃。糸を吐きまくります。
こちらの蜘蛛も、壬生狂言ゆかりの面を装着。ずっと顔隠してますが、見ると、怖いです。
連発される糸に苦しみながらも、獅子は蜘蛛を退治。
『攻め太鼓』に乗って勝利をアピールしまくって、めでたく結願。1時間20分の熱演でした。

奥の院から、公演が終わったばかりの舞台を眺める。
六斎の途中は意識しませんでしたが、改めて何の変化もない、いつも通りの清水寺です。

帰り、あんまり暑いから、六花亭でかき氷、食ったった。以上であります。
「8月は観光閑散期」とか言ったのは誰だ、というくらい、無茶苦茶に人多いです。
もちろん大半が、観光客。カップル率も、高し。で、その多くが典型的な観光ハイ。
この日はえらい暑さで、近くのバス駐車場から歩いてさえバテ果てるはずなんですが、
皆さん、脳内物質でも出てるのか、疲れ知らずのはしゃぎっぷりを見せてくれます。
六斎目当ての客は、おそらく、そんなに多くはありません。
陣取る人で舞台は埋まってますが、何かわからんけど釣られたという感じの人たちも、多し。
千日参りと六斎見物の人は地元感が強いですが、あとは完全にいつも通りの清水寺であります。
海外客が戻ってきたのか、外人率は欧米・アジア系とも高し。基本、団体ばっかり。
中国系団体は道の真ん中でも平気で立ち止まり、坂で大渋滞を発生させたりしてました。
日当たりのいいところでこれに捕まると、熱中症で死ぬかも知れないので、注意しましょう。
そんな、清水寺・盂蘭盆会の六斎念仏奉納。
好きな人と見たら、より六斎なんでしょう。
でも、ひとりで見ても、六斎です。

|
|
|
【客層】 (客層表記について) カップル:3 女性グループ:1 男性グループ:若干 混成グループ:2 子供:1 中高年夫婦:1 中高年女性グループ:1 中高年団体 or グループ:1 単身女性:若干 単身男性:若干 |
【ひとりに向いてる度】 ★ 色気・人圧・暑さが一丸となって襲いかかる、修羅の庭。 六斎は是非見てほしいが、場所が鬼門であることは否めない。 よく見えるからといって舞台の端にいると、 背後から阿呆に押されたり、あるいは密集による熱中症で、 ふらつき落下するかも知れないので、注意。 【条件】 |

清水寺・盂蘭盆会 六斎念仏奉納
たぶん毎年8月第一日曜に開催
15:00~
中堂寺六斎 公式 – 京都 中堂寺六斎会
清水寺
京都府京都市東山区清水1-294
6:00~18:00
京阪電車・清水五条駅下車 徒歩25分
京都市営バス「清水道」及び京阪バス「五条坂」
下車徒歩約15分
公式サイト 音羽山 清水寺
wikipedia 清水寺